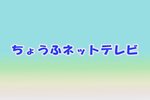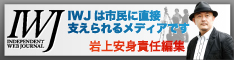2023年10月26日
さよなら、東京現像所
長きに渡って「映画のまち調布」で、映画・映像作品づくりに貢献してきた東京現像所が全事業を終了することになりました。
映画のことに詳しい矢ヶ崎雅代さんによる、東京現像所事業終了についての特集記事です。

写真提供:東京現像所
≪さよなら、東京現像所≫
「映画のまち調布」の中でも、撮影所と並んで歴史がある東京現像所が11月末で営業終了。
日本映画の黄金期、テレビ業界を支えてきた老舗の会社だけに残念です。
1950年代に入り、カラー映画が徐々に増加。
フィルム現像処理作業を安定して供給するため、1955年に創立され、その歴史は、日本映画界と共に歩んできました。
近年は、名作映画の4Kデジタルリマスター(修復)を行い、「七人の侍」「生きる」「細雪」「駅~ステーション~」等、数々の作品を手がけてきました。
調布ジュニア映画塾でも、子どもたちの企業見学会で大変お世話になっていました。
懐かしいフィルム専用の機材や最新鋭のデジタル機器があり、ここは映画のできあがる聖地だと思いました。
「撮影よりも、編集が一番重要」と言い切る映画監督も多く、ただ現像するだけでなく、最終工程の重要な編集の場でもあると。
渡り廊下には、数々の名作映画のポスター。
そして、試写ルームには、たくさんの映画監督が座った椅子。
壁のシミひとつにも、映画の息吹きを感じることができました。
特筆すべきは、デジタルリマスター(修復作業)をしている現場でした。
ひとつひとつの傷をPC画面で手作業で直している作業を観て、頭の下がる思いでした。
「フィルムで撮影するとね、淡い感じが出てすごくいいんだよ。デジタルでもできるのかもしれないけれど、かなり調整しないとね。なんでもくっきりはっきり映し出してしまうデジタルよりも、なんとなく淡く余白を残した風合いのフィルムの方が僕は好きだなぁ。」
と黄金期に活躍された映画監督からお聞きしたことがあります。
変わるは自然の理。
デジタル化は時代の流れであり、当然避けられないことですが、アナログの良さ、フィルムの風合いを東京現像所のことと共に次の世代へ伝えて行くことが、私たち昭和生まれの使命だと思いました。
最後に私の周囲の映像関係者の方々から、ひとことコメントをいただきました。
「トーゲン(東京現像所の愛称)がなくなってしまうことは、とても悲しいことです。特にフィルムの時代に、映画を作り始めた僕たちにとっては、言葉では言い尽くせないものがあります。」(映画監督50代)
「新人時代にオプチカルチェックや0号試写で何度か通いましたね。懐かしいフィルム時代の想い出です。」(元CM制作、70代)
※オプチカル 映画の合成技術
0号試写 編集が終了してチェックの済んだ完成形の初めての御披露目試写
「東現で沢山の映画などに触れた事は今の私の糧になっています。男性ばかりの職場で仕事振りを認めてもらい、女性の採用を増やしてくれたのも自信に繋がりました。出産で残念ながら退社しましたが、その後も映画や映像に携わり続けているのも、東現での時間があったから。ありがとう、そしてお疲れ様でしたと伝えたいです。」(東現OG、50代)
(文責:矢ヶ崎雅代)
なお、DI(Digital Intermediate=デジタルによる映画の色彩等の調整)事業、アニメ・テレビ作品の編集事業、映像デジタルアーカイブ事業については、事業終了の後、改めて東宝グループの中に承継されることになっているそうです。
(水谷)
映画のことに詳しい矢ヶ崎雅代さんによる、東京現像所事業終了についての特集記事です。

写真提供:東京現像所
≪さよなら、東京現像所≫
「映画のまち調布」の中でも、撮影所と並んで歴史がある東京現像所が11月末で営業終了。
日本映画の黄金期、テレビ業界を支えてきた老舗の会社だけに残念です。
1950年代に入り、カラー映画が徐々に増加。
フィルム現像処理作業を安定して供給するため、1955年に創立され、その歴史は、日本映画界と共に歩んできました。
近年は、名作映画の4Kデジタルリマスター(修復)を行い、「七人の侍」「生きる」「細雪」「駅~ステーション~」等、数々の作品を手がけてきました。
調布ジュニア映画塾でも、子どもたちの企業見学会で大変お世話になっていました。
懐かしいフィルム専用の機材や最新鋭のデジタル機器があり、ここは映画のできあがる聖地だと思いました。
「撮影よりも、編集が一番重要」と言い切る映画監督も多く、ただ現像するだけでなく、最終工程の重要な編集の場でもあると。
渡り廊下には、数々の名作映画のポスター。
そして、試写ルームには、たくさんの映画監督が座った椅子。
壁のシミひとつにも、映画の息吹きを感じることができました。
特筆すべきは、デジタルリマスター(修復作業)をしている現場でした。
ひとつひとつの傷をPC画面で手作業で直している作業を観て、頭の下がる思いでした。
「フィルムで撮影するとね、淡い感じが出てすごくいいんだよ。デジタルでもできるのかもしれないけれど、かなり調整しないとね。なんでもくっきりはっきり映し出してしまうデジタルよりも、なんとなく淡く余白を残した風合いのフィルムの方が僕は好きだなぁ。」
と黄金期に活躍された映画監督からお聞きしたことがあります。
変わるは自然の理。
デジタル化は時代の流れであり、当然避けられないことですが、アナログの良さ、フィルムの風合いを東京現像所のことと共に次の世代へ伝えて行くことが、私たち昭和生まれの使命だと思いました。
最後に私の周囲の映像関係者の方々から、ひとことコメントをいただきました。
「トーゲン(東京現像所の愛称)がなくなってしまうことは、とても悲しいことです。特にフィルムの時代に、映画を作り始めた僕たちにとっては、言葉では言い尽くせないものがあります。」(映画監督50代)
「新人時代にオプチカルチェックや0号試写で何度か通いましたね。懐かしいフィルム時代の想い出です。」(元CM制作、70代)
※オプチカル 映画の合成技術
0号試写 編集が終了してチェックの済んだ完成形の初めての御披露目試写
「東現で沢山の映画などに触れた事は今の私の糧になっています。男性ばかりの職場で仕事振りを認めてもらい、女性の採用を増やしてくれたのも自信に繋がりました。出産で残念ながら退社しましたが、その後も映画や映像に携わり続けているのも、東現での時間があったから。ありがとう、そしてお疲れ様でしたと伝えたいです。」(東現OG、50代)
(文責:矢ヶ崎雅代)
なお、DI(Digital Intermediate=デジタルによる映画の色彩等の調整)事業、アニメ・テレビ作品の編集事業、映像デジタルアーカイブ事業については、事業終了の後、改めて東宝グループの中に承継されることになっているそうです。
(水谷)